狩猟を始めたばかりの方にとって、
「どんな場所で猟ができるのか」は最初の大きな疑問ではないでしょうか。
ひとくちに“猟場”といっても、地形や環境、対象動物によって特徴がまったく異なります。
この記事では、日本で代表的な猟場の種類と、それぞれの特徴・注意点をわかりやすく解説します。
山間部(やまあい)の猟場
最もポピュラーなのが、山林を中心とした山間部の猟場です。
シカやイノシシなどの大型獣が多く生息しており、
足跡や食痕を探しながら獲物を追う「巻き狩り」や「忍び猟」が行われます。
山間部の魅力は、自然の中での緊張感と発見の多さです。
ただし、傾斜が急で足場が悪く、遭難や転倒の危険もあります。
地形を把握するために事前の下見(踏査)が欠かせません。
また、山主の許可が必要な場所も多いので、地元猟友会やベテランに同行してもらうのが安心です。
里山・農地まわり
次に多いのが、田畑や民家の近くに広がる里山エリアです。
人の生活圏に近いだけあって、有害鳥獣駆除や被害防止活動の場としても利用されています。
イノシシ、ハクビシン、アナグマなどの中型獣が多く、出没時間は早朝や夕方に集中します。
このような場所では、銃を使用する場合に安全角度の確保が非常に重要です。
発砲方向の先に住宅や道路がないか、常に確認する習慣をつけましょう。
また、農地の近くでは関係者とのトラブルを避けるため、事前の声かけやマナーを徹底することが大切です。
地域との信頼関係があってこそ、継続的に猟ができる環境が保たれます。
河川敷・湿地帯
カモ類やキジ、バンなどの水鳥猟でよく使われるのが、河川敷や湿地帯です。
平地で見通しが良く、射撃初心者でも比較的入りやすい猟場といえます。
ただし、河川法や漁業権の関係で、銃猟が禁止されている区域も多いので注意が必要です。
地元自治体や猟友会に確認してから入るようにしましょう。
また、水辺では足元が滑りやすいため、防水ブーツやウェーダーを用意しておくと安全です。
風向きや水鳥の習性を読んで、待ち伏せの位置を決めるのもこの猟場の醍醐味です。
島や沿岸部
少し珍しい例ですが、離島や海岸線も立派な猟場になります。
特に、海岸沿いではカモ猟やウミネコ猟などが行われています。
このような猟場は風や潮の流れに左右されるため、天候判断が命です。
波が高い日や強風の日は視界が悪く、銃の安全操作も難しくなります。
また、交通手段が限られる離島では、装備の忘れ物が命取りになることもあります。
出発前にしっかりと装備チェックをしておきましょう。
民有地・共有地での注意点
どの猟場にも共通するのが、土地の所有者への配慮です。
日本の山や林道のほとんどは民有地であり、「立ち入り禁止」の看板がある場所は基本的に入れません。
たとえ獲物の痕跡があっても、勝手に入るのはマナー違反です。
もし個人所有の山を使わせてもらう場合は、必ず事前に許可を取り、
「いつ・誰が・どこで猟をするのか」を明確に伝えましょう。
信頼を積み重ねることで、次回以降も安心して猟を続けることができます。
まとめ
| 猟場の種類 | 主な対象 | 特徴 |
|---|---|---|
| 山間部 | シカ・イノシシ | 地形が険しいが獣が多い |
| 里山 | イノシシ・ハクビシン | 住宅地に近く安全確認が必須 |
| 河川敷・湿地 | カモ・キジ | 平地で見通しが良い |
| 島・沿岸部 | 水鳥 | 天候・潮に注意 |
| 民有地 | さまざま | 許可が必要・マナー重視 |
猟場は場所によって環境もルールも異なります。
どの猟場にも共通して言えるのは、「安全第一」「地域との信頼」「事前準備」の3つです。
自分の猟のスタイルや体力、道具に合ったフィールドを選び、
その土地の自然と人に敬意を払いながら楽しむことが、長く狩猟を続ける一番のコツだと思います。

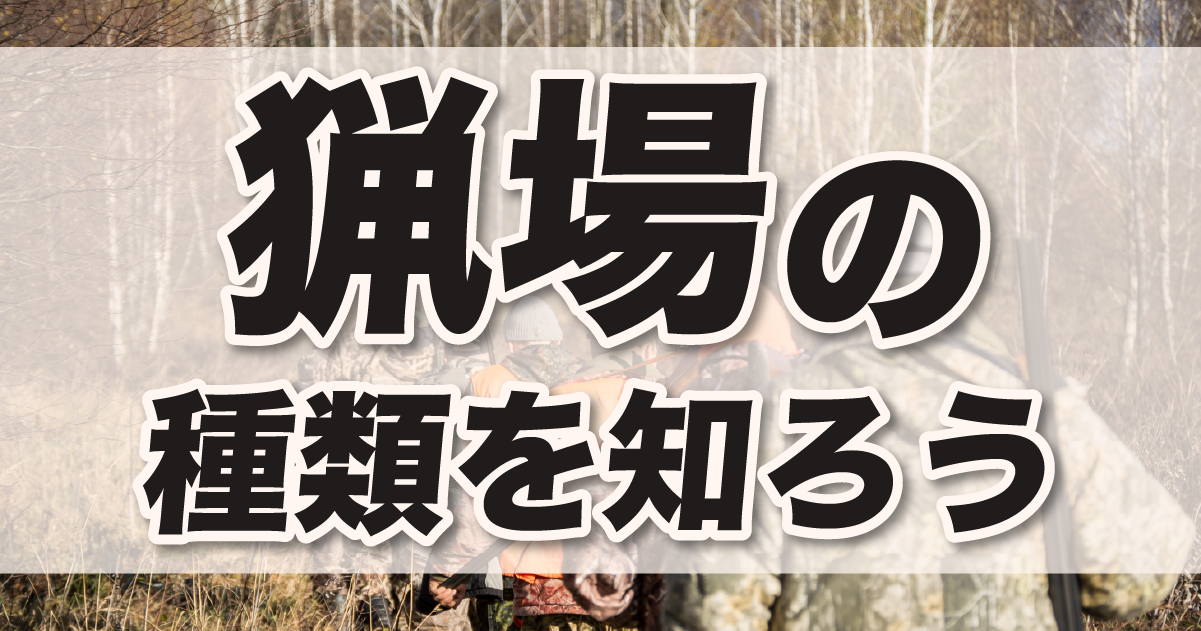
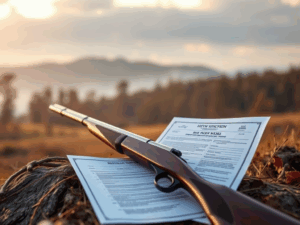

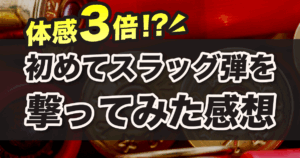



コメント